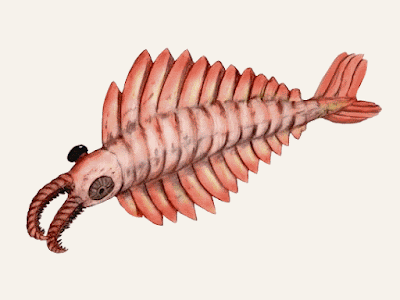日本産のヘビ類の一覧を示すとともに、各種類の生態(毒・分布・餌・繁殖など)を、生物学博物館学芸員の筆者がフリー画像をまじえながら図鑑形式で解説します。
メクラヘビ科
ブラーミニメクラヘビ

ブラーミニメクラヘビは、東南アジア原産と考えられており、現在は世界各地の熱帯~亜熱帯地域に人為移入(輸入観葉植物の土に卵が混入して)されています。日本では沖縄県に分布しています。分布域では平地の草原や耕作地の倒木や石の下に生息しています。無毒です。シロアリなど土壌性の小型節足動物を捕食します。メスのみの単為生殖・卵生で繁殖期の6~7月に産卵します。
個別解説記事
セダカヘビ科
イワサキセダカヘビ

イワサキセダカヘビは、日本固有種で、石垣島と西表島に分布しています。基本的には樹上性と考えられていますが、地上を匍匐することもあります。毒牙自体が退化しており無毒です。カタツムリを専食するというかわった食性を持っており、右巻きが大多数のカタツムリ捕食に特化した顎・歯構造をしていて、効率よく食べられるように右顎には平均25本、左顎には平均18本と左右非対称になっています。
個別解説記事
タカチホヘビ科
タカチホヘビ

タカチホヘビは、本州・四国・九州に分布しており、亜種のアマミタカチホヘビ・タイワンタカチホヘビ・ヤエヤマタカチホヘビが奄美諸島〜南西諸島にかけて分布しています。国外では中国・ベトナムに分布しています。分布域では森林に生息しています。無毒です。落ち葉や倒木の下にいることが多く、そのような環境で捕食しやすいミミズや昆虫の幼虫を餌にしています。卵生で7〜8月に産卵します。
個別解説記事
ナミヘビ科
リュウキュウアオヘビ

リュウキュウアオヘビは、奄美諸島から沖縄諸島にかけて分布しており、亜種のサキシマアオヘビが八重山諸島と宮古島に分布しています。分布域では平地から山地にかけての森林に生息しています。無毒です。主にミミズを捕食しています。卵生で繁殖期の7月に産卵します。
ジムグリ

ジムグリは、日本固有種で北海道・本州・四国・九州に分布しています。分布域では平地から低山地にかけての森林・草原に生息しています。無毒です。モグラやネズミなど小型哺乳類を主な餌としています。特に巣の中にいる生まれたての幼獣を好むことが知られています。
アオダイショウ

アオダイショウは、日本固有種で、北海道・本州・四国・九州とその周辺諸島に分布しています。分布域では平地から山地にかけての森林・草原・市街地など幅広い環境に生息しています。樹上性傾向が強いものの、地面でも活動します。無毒です。鳥類(成鳥・雛・卵)やネズミなど小型哺乳類を捕食します。幼蛇はトカゲ・カエルなど両性爬虫類も餌にします。
シマヘビ

シマヘビは、北海道・本州・四国・九州に分布しています。分布域では河川周辺域を中心として森林や草原に生息しています。無毒です。カエル・トカゲ・小鳥・小型哺乳類などを捕食します。卵生で繁殖期の7〜8月に産卵します。
スジオナメラ

スジオナメラは、インドから東南アジア・台湾・先島諸島にかけてのアジアの亜熱帯〜熱帯域に広く分布しており、日本には亜種のサキシマスジオが分布しています。分布域では農耕地や民家周辺などで見ることができます。無毒です。主にネズミなど小型哺乳類を捕食しますが、時に小鳥やカエルを餌にすることもあります。卵生で繁殖期の6〜7月に産卵します。
シュウダ

シュウダは、中国南部〜台湾〜与那国島に分布しており、国内のものは亜種のヨナグニシュウダと呼ばれています。分布域では平地〜低山地の森林・草原・河川周辺に生息しており、農耕地で見られることもあります。無毒ですが、非常に強い臭気のする分泌液を総排泄孔から出します。ネズミなど小型哺乳類・小鳥・カエル・トカゲなど陸上脊椎動物を餌にしています。卵生で繁殖期の7月に産卵します。
ガラスヒバァ

ガラスヒバァは、日本固有種で奄美諸島と沖縄諸島に分布しています。分布域では平地〜低山地の湿潤な環境地域に生息しています。牙が小さく実被害例がないものの強い毒を持つことが、近年明らかになりました。カエル・ヤモリ・トカゲのほか水中の小魚も捕食します。卵生で繁殖期の5〜8月に産卵します。
ヒバカリ

ヒバカリは、本州・四国・九州に分布しており、国外ではロシア・中国・朝鮮半島に分布しています。分布域では平地から低山地の水辺周辺に生息しています。無毒です。カエルやトカゲのほか、水中にいるオタマジャクシや小魚も捕食します。卵生で繁殖期の7〜8月に産卵します。
アカマタ

アカマタは、日本固有種で奄美諸島と沖縄諸島に分布しています。分布域では平地から低山地にかけての河川周辺など湿潤な環境に生息しています。無毒です。小型哺乳類・鳥類・両性爬虫類のほか水中の小魚も捕食します。卵生で繁殖期の夏に産卵します。無毒です。小型哺乳類・鳥類・両性爬虫類のほか水中の小魚も捕食しますが、特にネズミや小鳥などを好みます。卵生で繁殖期の6〜7月に産卵します。
アカマダラ

アカマダラは、ロシア南部・中国・東南アジア・朝鮮半島・台湾・南西諸島に分布しており、国内には亜種のサキシママダラが八重山諸島と宮古諸島に分布しています。分布域では平地から低山地の森林・草原・河川周辺に生息しており、基本的には地上性ですが木に登ることもあります。無毒です。小型哺乳類・鳥類・両性爬虫類のほか水中の小魚も捕食しますが、特にネズミや小鳥などを好みます。卵生で繁殖期の6〜7月に産卵します。
シロマダラ

シロマダラは、日本固有種で、北海道・本州・四国・九州と周辺の島々に分布しています。分布域では低山地の森林に生息しています。無毒です。トカゲやヤモリなど小型爬虫類を捕食します。卵生で繁殖期の夏に産卵します。
ヤマカガシ

ヤマカガシは、日本固有種で本州・四国・九州・南西諸島に分布しています。また近似種が中国と朝鮮半島にいることが知られています。分布域では平地の湿潤な環境(水田や河川周辺)に生息しています。血液凝固作用を持つ毒を持っています。毒牙が奥歯にあることから咬傷事故例が少なく、かつては無毒ヘビと考えられていましたが、死亡事故も発生しています。主にカエルを餌にしていますが、イモリ・カナヘビ・ドジョウなども捕食します。卵生で繁殖期の7月に産卵します。
個別解説記事
コブラ科
ヒャン(ハイ)

ヒャンは、日本固有種で奄美諸島と沖縄諸島に分布しています。沖縄諸島のものは亜種のハイとして扱われています。分布域では乾燥気味の石灰岩土壌の広葉樹林帯に生息しています。ハブ毒の4〜5倍の強さとも言われる神経毒を持っていますが、小型で毒量自体が少ないため危険種とはされていません。昆虫などのほか小型の爬虫類も捕食することがあります。卵生で繁殖期の6月に産卵します。
ワモンベニヘビ

ワモンベニヘビは、インド亜大陸〜東南アジア〜台湾〜中国に分布しており、国内には亜種のイワサキワモンベニヘビが石垣島と西表島に分布しています。分布域では広葉樹林帯に生息しています。有毒ですが毒性は低く、また口が小さいためこれまで事故例はなく危険なヘビとは見なされていません。他のヘビ(メクラヘビ・サキシママダラ)を捕食します。卵生で繁殖期の夏に産卵します。
クロガシラウミヘビ

クロガシラウミヘビは、東南アジアからオセアニアにかけて分布しており、国内では南西諸島から沖縄諸島にかけて見られます。砂地の海水域に生息しています。非常に強い神経毒を持つとともに、やや攻撃的な性質をしているため沖縄県では死亡例も少なくありません。魚食性で、主にアナゴ類を捕食しています。卵胎生で10月頃に幼蛇を産みます。
クロボシウミヘビ

クロボシウミヘビは、東南アジア・オーストラリア・台湾・南西諸島に分布しています。分布域では砂礫底の海水域に生息しています。非常に強い神経毒を持ち、なおかつ高い攻撃性を持つためウミヘビ類のなかでも最危険種とされています。卵胎生で10月頃に幼蛇を産みます。
アオマダラウミヘビ

アオマダラウミヘビは、インド洋東部から西太平洋にかけて広く分布しています。海洋性の強い夜行性で、日中は海岸近くの岩の割れ目などにいます。強い神経毒を持ちますが、口が小さく攻撃性も低いため、危険種とはさていません。しかし注意は必要です。卵生で海岸の岩の割れ目などに産卵します。
エラブウミヘビ

エラブウミヘビは、東南アジア〜台湾〜中国にかけての南シナ海・東シナ海に分布しており、日本では西表島・石垣島・宮古島などに分布しています。分布域ではサンゴ礁周辺に生息しています。非常に強い神経毒を持っているものの、口が小さく攻撃性も低いため危険種とはされていません。しかし、扱いに注意は必要です。サンゴ礁に住むウツボ類・ギンポ類・スズメダイ類・ハゼ類・ベラ類などを餌にしています。卵生で繁殖期の夏〜秋に海岸の岩の割れ目などに産卵します。
ヒロオウミヘビ

ヒロオウミヘビは、インド洋東部から西太平洋にかけて分布しています。極めて強い神経毒を持つ危険種です。アナゴ類やウツボ類を捕食します。卵生で海岸の岩の割れ目などに産卵します。
イイジマウミヘビ

イイジマウミヘビは、フィリピン〜台湾〜南西諸島にかけて分布しています。分布域では沿岸部に生息しており、海洋性で陸に上がることはありません。有毒種として特定動物に指定されています。スズメダイやギンポ類の魚卵を餌にしています。卵胎生で一度に5匹ほどの幼蛇を産みます。
セグロウミヘビ

セグロウミヘビは、インド洋・太平洋の暖かい地域に分布しており、日本でも多くの確認・記録があります。外洋性で陸上に上がることはありません。有毒種として特定動物に指定されています。魚食性で主に小魚を捕食します。卵胎生で一度に2〜6匹の幼蛇を産みます。
個別解説記事
クサリヘビ科
ハブ

ハブは、日本固有種で南西諸島に分布しており、八重山諸島には亜種のサキシマハブが分布しています。分布域では平地から山地にかけての森林・草原・農耕地などに生息しており、樹上でも地上でも活動します。毒自体はマムシよりも弱毒性ですが、一回の毒量が非常に多いため重篤な事故が多数発生しています。主にネズミなど小型哺乳類を捕食しますが、このほかに小鳥・爬虫類・両生類・魚類も餌にします。卵生で繁殖期の7月に産卵を行います。
ヒメハブ

ヒメハブは、日本固有種で奄美諸島と沖縄諸島に分布しています。分布域では水田周辺や湿潤な森林に生息しています。毒はハブに比べるとかなり弱く、また一回の毒量も多くないため重篤な咬傷事故はありません。主にネズミなど小型哺乳類を中心として爬虫類・両生類および水中の魚類も捕食します。卵胎生に近い卵生で繁殖期の7〜8月に産卵します。産み落とされた卵は数日で孵化します。
ニホンマムシ

ニホンマムシは、日本固有種で北海道・本州・四国・九州に分布しています。分布域では平地から山地にかけての森林・水田・河川周辺など水辺または湿潤な場所に生息しています。毒は複数のタンパク毒の組み合わせで、極度に強い毒性はないものの咬傷による死亡例もあり注意が必要です。ネズミやリスなど小型哺乳類を中心として鳥類・爬虫類・両生類のみならず水中の魚類も捕食します。卵胎生で繁殖期の8〜10月に幼蛇を産みます。