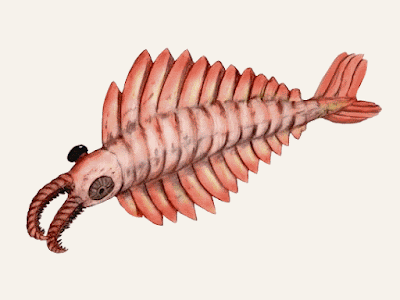ヒヨケムシの生態について解説するとともに、20年以上、生物学学芸員として博物館施設に勤務し、昆虫が専門分野の一つである筆者が、その飼育方法についてご紹介していきます。
ヒヨケムシとはどんな生き物?
ヒヨケムシ(ヒヨケムシ類、学名: Solifugae)は、鋏角亜門クモガタ綱に分類される節足動物の分類群の一つ。分類学上はヒヨケムシ目とされる。強大なはさみ型の鋏角と脚のような触肢を先頭に有し、主に砂漠に生息する俊敏な捕食者である。一見クモにも似た姿だが、クモではない。研究は少なく、その形態・生態・系統に関しては未だに不明点が多い。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/ヒヨケムシ
ヒヨケムシの分類

ヒヨケムシはなんの仲間?
ヒヨケムシはクモガタ網ヒヨケムシ目に属する生物の総称で、世界で約1100種が知られています。なお、ヒヨケムシ目には以下の科が含まれます。
スナハシリヒヨケムシ科 Ammotrechidae
ミナミヒヨケムシ科 Ceromidae
コヒヨケムシ科 Daesiidae
ヒトリヒヨケムシ科 Eremobatidae
サメヒヨケムシ科 Galeodidae
アジアヒヨケムシ科 Gylippidae
アナホリヒヨケムシ科 Hexisopodidae
カルシュヒヨケムシ科 Karschiidae
ウモウヒゲヒヨケムシ科 Melanoblossidae
ヒカラビヒヨケムシ科 Mummuciidae
オオヒヨケムシ科 Rhagodidae
ヒヨケムシ科 Solpugidae
ヒヨケムシの主な種類
スナホリヒヨケムシ科のChinchippus peruvianus

コヒヨケムシ科のGluvia dorsalis Gluvia dorsalis

ヒトリヒヨケムシ科の一種
.jpg/800px-Eremobatine_solifugid_(8689233067).jpg)
サメヒヨケムシ科のGaleodes caspius

オオヒヨケムシ科の一種

ヒヨケムシ科のSolpugema hostilis

ヒヨケムシの基本情報
ヒヨケムシの原産地

ヒヨケムシは世界の熱帯から亜熱帯にかけての乾燥地帯(砂漠地帯)に分布していますが、オセアニアには分布していません。
ヒヨケムシの寿命

ヒヨケムシの寿命はあまり長くなく、1〜2年であると考えられています。
ヒヨケムシは毒がある?

ヒヨケムシは毒々しい外見をしているため、有毒生物だと誤解されがちですが、実際には毒はありません。ただし、その大顎は強靭なため、噛まれると怪我をしますので素手では扱わないようにしてください。
ヒヨケムシは脱皮する?

ヒヨケムシの身体の構造

ヒヨケムシはクモとサソリの中間的な構造をしており、ハサミのついた触肢と第1〜4歩脚、つまり二本の腕と八本の脚を持っています。
ヒヨケムシの顎の構造

ヒヨケムシの捕食において最重要な働きをするのが、その屈強な大顎ですが、かなり特殊な構造をしています。
上から見ると左右に一個ずつ一対の顎を持っていますが、それぞれの顎は上下に挟む構造のハサミ状になっています。
節足動物の顎はもともと脚由来の器官であり、まだ脚としての機能が残った原始的な形質であることがわかります。

この写真のように、斜め上方から見ると、その顎の構造が観察しやすいです。

ヒヨケムシは乾燥地帯の生き物ですので、湿度を嫌います。プラケースに清潔な乾いた砂を入れ、隠れ家になる枯れ枝などを配置します。

この写真のように、斜め上方から見ると、その顎の構造が観察しやすいです。
ヒヨケムシの飼い方
ヒヨケムシの飼育環境

ヒヨケムシは乾燥地帯の生き物ですので、湿度を嫌います。プラケースに清潔な乾いた砂を入れ、隠れ家になる枯れ枝などを配置します。
種類によっては砂を掘って穴を作り、そこに潜む習性があるので、砂は深めに5cmほど入れるとよいでしょう。
また、熱帯から亜熱帯にかけて生息しているため、寒さには強くありません。プラケースの下にマットヒーターを敷いて気温25℃以上を保つようにします。
水分は後述の餌の持つ水分で十分ですので、給水や霧吹きの必要はありません。

ヒヨケムシほ捕食者ですので、基本的には生き餌しか食べません。手間と栄養バランスを考慮すると、餌コオロギを週に2回、一度に2〜3 匹ずつ与えるとよいでしょう。

雌雄のタイミングが合うと、交接したのちメスは産卵します。メスが拒否した場合、多くの場合オスは捕食されてしまいます。また、うまく交接した場合も、逃げ遅れるとオスは捕食されてしまいます。
ヒヨケムシの餌

ヒヨケムシほ捕食者ですので、基本的には生き餌しか食べません。手間と栄養バランスを考慮すると、餌コオロギを週に2回、一度に2〜3 匹ずつ与えるとよいでしょう。
ヒヨケムシの繁殖のさせ方

雌雄のタイミングが合うと、交接したのちメスは産卵します。メスが拒否した場合、多くの場合オスは捕食されてしまいます。また、うまく交接した場合も、逃げ遅れるとオスは捕食されてしまいます。
多くのヒヨケムシの種は土中に巣を掘り、そこに卵を産み、種類によっては孵化するまでメス親が保護をします。