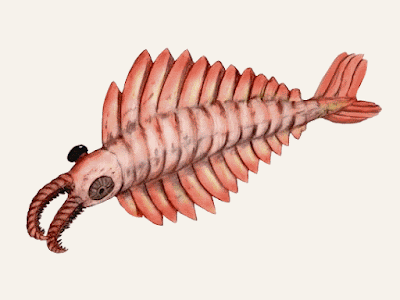ヌマエビの家庭水槽(アクアテラリウム)での初心者向き飼い方を博物館学芸員の筆者が、長年の経験をもとに解説します。
ヌマエビとはどんな生き物?
ヌマエビ科(ヌマエビか、学名 Atyidae )は、エビの分類群の一つ。ヌマエビ、ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビなど、熱帯から温帯の淡水域に生息するエビを含む分類群である。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/ヌマエビ科
日本で見られるヌマエビの主な種類
オニヌマエビ Atyopsis spinipes
ヤマトヌマエビ Caridina multidentata
.jpg)
トゲナシヌマエビ C. typus H. Milne

ミゾレヌマエビ C. leucosticta

ヒメヌマエビ C. serratirostris

ミナミヌマエビ Neocaridina denticulata

ヌマエビの特徴と飼い方
適正水質:中性~弱酸性適正水温:0~25℃
餌の種類:水槽に生える藻類
繁殖:一部種類は容易
混泳:可能
ヌマエビはヌマエビ科の淡水エビの総称であり、さまざまな種が含まれます。
いずれの種も草食性でおとなしいため、他の小型魚類との混泳に適しています。
ほとんどの種のゾエア幼生が汽水域で育つため繁殖は難しいですが、抱卵した親エビを15‰(パーミル)程度の汽水に移すとゾエア幼生を放出します。ゾエア幼生はかなり小さいため、餌としてワムシを用意して与えます。
このように、回遊性ヌマエビ類の産卵・繁殖にはそれなりの設備と準備が必要となるため、不可能ではありませんがかなり困難です。
一方、ヌマエビ・ヌカエビ・ミナミヌマエビの陸封型は、稚エビになるまで親が抱卵してから淡水に放出するので、飼育下の水槽内で勝手に増えるほど繁殖は容易です。
いずれの種も高水温と酸欠には弱いので、しっかりと対策をする必要があります。
※遺伝子のかく乱を避けるため、入手した生物は野外へは放流せずに必ず最後まで飼いきるようにしてください。
※日本産生物は種類・地域により保護されている場合がありますので、野外採集はせずブリード個体を入手してください。

「アクアテラリウム」とは陸場と水場がある形式の水槽システムのことで、魚類以外の多くの水生昆虫・甲殻類・両生類・爬虫類を飼育する場合に必要になります。
アクアテラリウムでは、通常の水槽と違って水量が半分程度になりますので、あまり小さな30cmや45cmの水槽では水質が安定しません。やはり60cmクラス以上の水槽が必要でしょう。また、陸場を広くとるためには奥行き30cmタイプではなく45cmタイプをおすすめします。
詳しくは下記の関連記事で必要な機材から具体的な組み立て方まで解説していますのでご参照ください。

アクアテラリウムの作り方と飼育生物一覧|博物館学芸員が必要な器材を解説

日本産淡水魚の家庭飼育向きの種類を厳選し解説しているのが下記の記事です。魚類飼育歴20年以上の博物館学芸員が執筆したものです。
日本の淡水魚・飼育種類図鑑|それぞれの特徴と家庭水槽での飼い方(水槽のセット方法)
一方、ヌマエビ・ヌカエビ・ミナミヌマエビの陸封型は、稚エビになるまで親が抱卵してから淡水に放出するので、飼育下の水槽内で勝手に増えるほど繁殖は容易です。
いずれの種も高水温と酸欠には弱いので、しっかりと対策をする必要があります。
※遺伝子のかく乱を避けるため、入手した生物は野外へは放流せずに必ず最後まで飼いきるようにしてください。
※日本産生物は種類・地域により保護されている場合がありますので、野外採集はせずブリード個体を入手してください。
アクアテラリウムとは

「アクアテラリウム」とは陸場と水場がある形式の水槽システムのことで、魚類以外の多くの水生昆虫・甲殻類・両生類・爬虫類を飼育する場合に必要になります。
アクアテラリウムでは、通常の水槽と違って水量が半分程度になりますので、あまり小さな30cmや45cmの水槽では水質が安定しません。やはり60cmクラス以上の水槽が必要でしょう。また、陸場を広くとるためには奥行き30cmタイプではなく45cmタイプをおすすめします。
詳しくは下記の関連記事で必要な機材から具体的な組み立て方まで解説していますのでご参照ください。
関連記事

アクアテラリウムの作り方と飼育生物一覧|博物館学芸員が必要な器材を解説
日本産淡水魚・飼育種類図鑑

日本産淡水魚の家庭飼育向きの種類を厳選し解説しているのが下記の記事です。魚類飼育歴20年以上の博物館学芸員が執筆したものです。
日本の淡水魚・飼育種類図鑑|それぞれの特徴と家庭水槽での飼い方(水槽のセット方法)